なぜ日本のDXは遅れているのか?
1、「紙文化」や「ハンコ文化」の根強い定着
日本の企業では、請求書・契約書・経費精算などの多くが紙ベースで行われており、DXの妨げになっています。
例えば、経費精算業務において「すべての処理を紙またはExcelで行っている」と回答した企業は46.2%にのぼります。
また、企業間での電子契約の利用率はわずか24.7%と依然として低く、70%以上の企業が依然として紙の契約書を交わしている実態があります。
[出典:デジタル庁「企業におけるデジタル取引実態調査2023」]
このような紙文化が変革の障壁となり、デジタル化の重要性を理解しつつも実行に踏み出せない企業が多いのが現状です。
2、老朽化したレガシーシステムの存在と統合性の欠如
経済産業省の「DXレポート」では、古いITシステムのまま放置すると「2025年の崖」に直面し、年間最大12兆円の経済損失が生じるとされています。
[出典:経済産業省 DXレポート]
日本企業の約60%が20年以上前に構築したシステムを現役で使用しており、約70%の企業でシステム連携が不十分という課題があります。20年前の会計システムを使い続けたり、クラウドと連携できずデータが分断されている企業も多く、これがDX推進の大きな障害となっています。
3、DXを単なる効率化と誤認している企業が多い
欧米などでは「DX=新たな価値創出とビジネスモデル変革」という考え方が浸透していますが、日本では異なる状況です。
日本企業の約半数(49.2%)が「DX=システム導入・IT活用」と考え、「ビジネスモデルの変革」と捉えている企業はわずか27.3%に留まっています。この認識の違いが、単なる業務効率化にとどまり、真の競争力強化につながらない原因となっています。
世界のDXはどこまで進んでいるのか?
欧米:中国:シンガポールの先進事例
【欧米】
電子契約サービス(例:DocuSign、Adobe Sign)の普及により、契約手続きの完全デジタル化が進み、米国では企業契約の約70%が電子契約で締結されています。
QuickBooks(米国)、Xero(英国)など、クラウド会計が主流になっており、米国では中小企業の80%以上がクラウド会計を導入しています。
【中国】
モバイル決済(Alipay、WeChat Pay)がビジネスでも一般化し、中国の小売決済の87.6%がモバイル決済となっています。
AIによる経理業務(帳簿整理・経費精算)の自動化が進行し、大手企業の約60%が何らかのAI会計システムを導入済みです。
【シンガポール】
政府主導の「Go Digital」政策により、中小企業の86%がデジタルツールを活用しています。
電子請求書の義務化と行政手続きの完全オンライン化が実現し、企業の99%以上が電子請求書システムを導入済みです。
巻き返しの第一歩は「経理部門のDX」から
具体的に何から始めるべきか?
① 電子契約・電子請求書の導入
紙の契約書から脱却し、DocuSignやクラウド請求書ツールを活用することで、契約締結時間を平均80%短縮できることがわかっています。また、2023年10月から開始されたインボイス制度への対応としても電子請求書は有効で、業務効率・コンプライアンス両面でメリットがあります。
[出典:国税庁 電子インボイス制度]
② クラウド会計・経費精算システムの活用
クラウド会計でリアルタイムな数値把握が可能になり、決算業務が平均45%効率化されるというデータが公表されています。AI経費精算システムでは、入力ミスや二重作業を削減することにより、経費処理時間が約70%削減された事例も多数報告されています。
③ RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)による自動化
繰り返し作業をRPAで置き換えることで、人的リソースの有効活用が可能になります。RPA導入企業の多くが業務時間の30%以上削減に成功しており、ミスの削減と生産性向上を同時に実現し、経理部門の戦略的業務へのシフトが可能になります。
まとめ|今こそ経理部門から始めるDXで、日本の巻き返しを
日本のDXは、紙文化、レガシーシステム、誤ったDX認識といった構造的課題により遅れを取っているのが現実です。IMD世界デジタル競争力ランキングでは、日本は64か国中32位と、主要先進国の中では依然として低い位置にとどまっています。
しかし、世界の先進事例を踏まえ、まずは経理・財務といったバックオフィスから段階的にDXを進めることで、十分な巻き返しが可能です。中小企業庁のデジタル化支援事業も積極的に活用しながら、今こそ、「変革の覚悟」と「継続的な実行力」を持って、デジタル化の第一歩を踏み出す時です。
[出典:中小企業庁「デジタル化支援ポータル」]




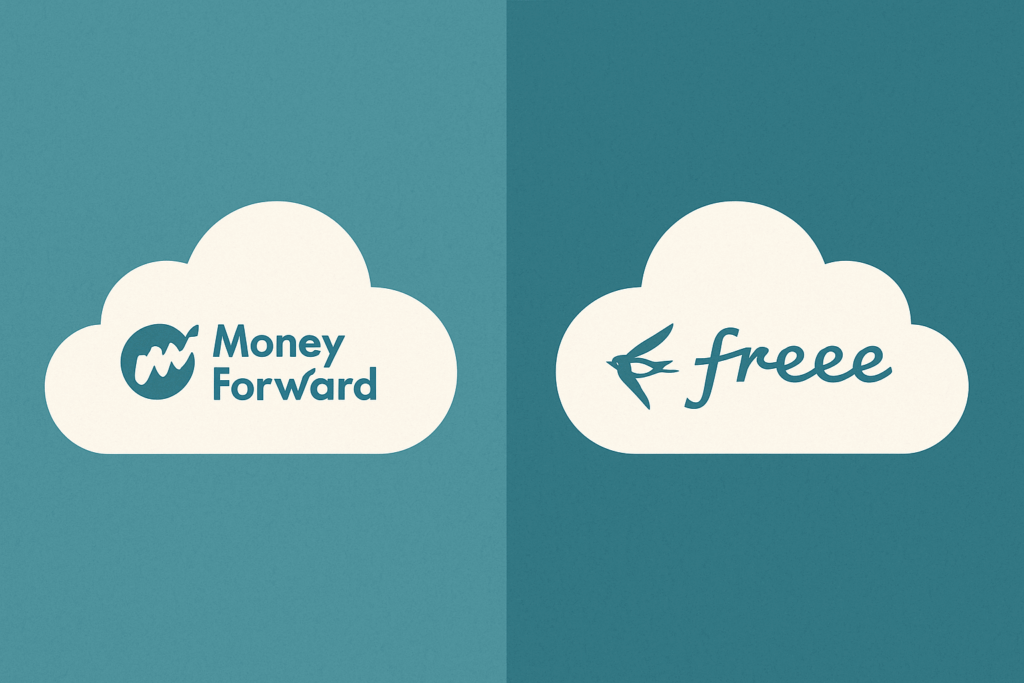
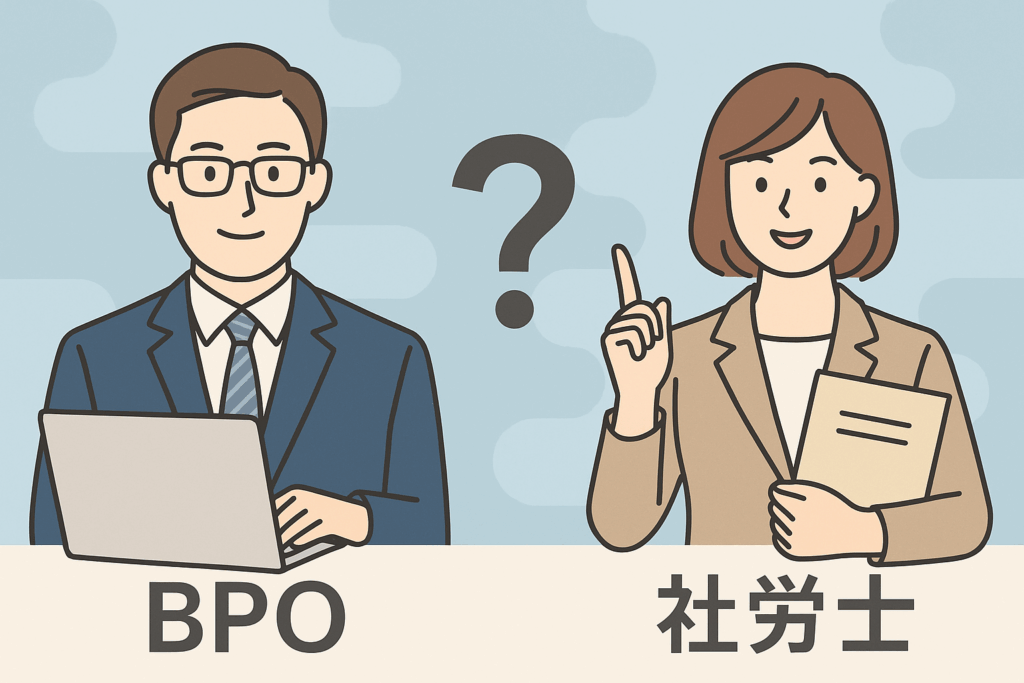
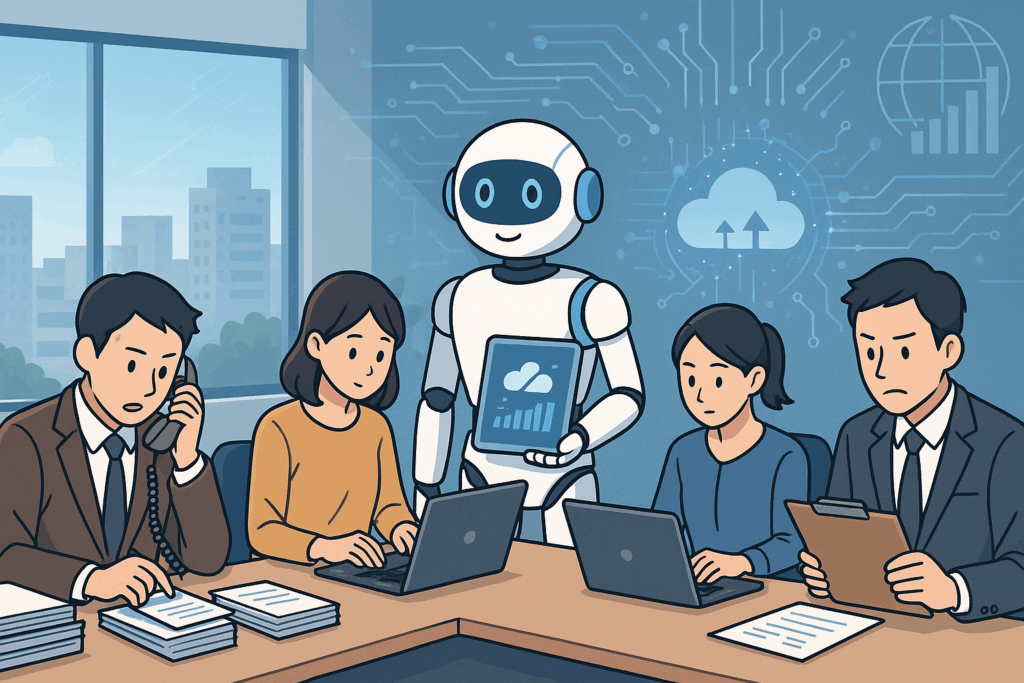

No comment yet, add your voice below!